南極OB会北海道支部では、日本ではじめて南極探検を行った白瀬矗中尉の南極探検100周年記念事業として、下記の通りイベントを計画しています。
この事業は、「白瀬日本南極探検隊100周年記念プロジェクト実行委員会」が中心となり、南極OB会も共に進めている全国規模のイベントです。
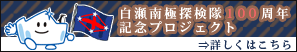
| と き | 平成23年7月24日(日)12:00〜17:00 |
| ところ | 北海道大学 学術交流会館
(札幌市北区北八条西五丁目。北大正門付近) |
| 公演 | 13:00〜
「白瀬南極探検隊と蝦夷地」
講師:澤柿教伸(第34次、47次越冬隊員)
「南極で食べるということ」
講師:西村 淳(第30次、38次越冬隊員) |
| 展示・体験コーナー | 「白瀬南極探検隊」
日本初のドキュメンタリー映像を上映
「タペストリー展示」
白瀬南極探検隊記念館提供タペストリーを展示
「南極地域観測隊装備品展示」
羽毛服などを実際に着用して記念撮影
「南極の氷に触れよう」
南極で採取した氷を展示
「南極昭和基地LIVE映像」
昭和基地のLIVE映像を中継 |
「白瀬南極探検」100 周年記念事業趣意書
南極OB会北海道支部 支部長 前晋爾
今から100 年前、アムンゼン隊やスコット隊による人類初の南極点到達を国家事業として競っていた1910 年(明治43 年)、白瀬矗(のぶ)中尉は南極探検隊を組織し、国民の圧倒的な支持で得られた資金のみで、政府の援助がないまま、同年11 月29 日、長さ30m、幅7m、積載量204 トン、わずか18 馬力の木造機帆船「開南丸」で南極を目指しました。開南丸は、赤道を越え南半球を入った日本で初めて船舶でした。
翌1911年3月、南極大陸を指呼の間に見ながらも、冬の到来で海が結氷を始めたため南下をあきらめ、シドニーに戻りました。準備を整えながら南半球の冬をやり過ごして再出発し、西南極大陸ロス棚氷のくじら湾に上陸。1912 年1 月28 日南緯80度に達し、付近一帯を「大和雪原」と命名しました。大和雪原は南極の地図に名を留め、白瀬も昭和基地南方の「しらせ氷河」に名を残し、南極観測の輸送と支援にあたる砕氷艦の艦名「しらせ」も「しらせ氷河」に由来します。
戦後間もない日本が「国際地球観測年」に参加できたのは、白瀬探検隊の実績が国際社会から認められていたからでした。
100 年も前に、貧弱な船と装備で、厳しい南極に挑んだ人々と、それを熱狂的に支援した国民がいて、進取の気概をもって未知なる自然に挑戦し、一命を損することもなく探検を終えた事実を、100 周年を機会に、我が国の多くの人々、特に青少年諸君に伝えることは、南極観測に従事した我々南極OBの責務と考えています。
そのため、全国各地で講演会や展示会を開催し、当時の関係各国から講師を招いて国際講演会を開催するなど、白瀬探検隊の顕彰事業を行うとともに、白瀬による南極探検の意義を改めて考える機会を持つべく、100 周年記念事業を計画致しました。
ここに、皆様のご協力とご支援を賜りたく、よろしくお願い申しあげる次第です。
2011.6.30公開(7.13更新)